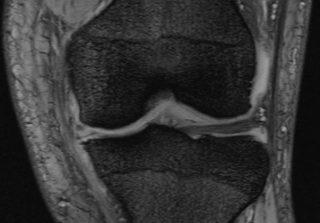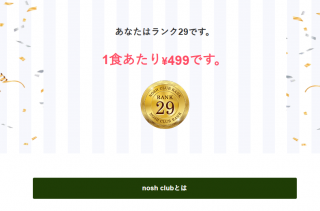こんにちは、Asです。今回は少しだけ真面目なお話を書いてみようと思います。
弊社はエンジニアのみなさんに年間目標の設定をして頂いています。
私はユニットマネージャーという立場にあり、統括するチームメンバーの皆さんの年間目標をチェックするのが仕事の1つです。
しかし、その『目標』は、まさに千差万別。内容もバラエティ豊かですし、目標と定める方向性も人それぞれです。
苦手を克服しようという方もいれば、得意分野を伸ばしたい人。仕事の幅を広げるために、新しい技術・言語の習得に力をいれる方…。
どれが良くて、どれが悪いという物は、当然ですが全くなくて、どれもが大切な目標です。
しかし、目標は決めただけではただの文字列、もしくは貼り紙。
達成しようと努力してこそ、その価値が生まれてきます。
ここで敢えて『達成してこそ』と言わないのには理由があります。
例えば資格試験を目標に掲げた方は、合格が目標のゴールです。大抵は「合格すること」を目標としますし、受験するだけでおしまい、結果は問わない――とは、しないはずです。
しかし無事に試験に合格しても、それで終わり! では勿体ないですよね。
取得した資格、もしくは資格を得るために学んだ知識・技術を仕事などに活かしてこそ、資格を取った価値が生まれてきます。
もしくは、残念ながら合格には届かなかったとしても、受験のために学習したことは、本人のスキルとして確実に加算されています。努力したことは、無駄になったりしないのです。
今回は駄目でも、結果を基に更なる勉強を続ければ、次回は合格するかもしれません。
目標に向けて己の学びを進めること、そして、学びを無駄にしないこと。
それこそが、本当の意味での『目標に向けて頑張った成果』ではないかと、私は考えています。
……とはいえ、仕事やプライベートで忙しく、目標に向けて頑張る時間を作り出すのが難しいことも多々あると思います。
では、どうすれば目標に向けて頑張ろうと、皆さんに思って貰えるのでしょうか。
これがユニットマネージャーとしての私には、かなり重要なポイントとなります。
この達成へのプロセスは色々なルートがあります。それこそ人それぞれで、多種多様な捉え方があるでしょう。
これから書くことが正しいとは言い切れません。あくまで『いまの私』が、目標設定の方法やコーチングの動画や書籍を読んで考えて来た内容をまとめたものです。
もしかしたら来年になったら違うことを言っているかもしれませんが、いったん己のためのアウトプットとして記させて頂きます。
さて、まず目標について考えた時、『ゴール(達成したいこと)を主眼におくか、プロセス(達成までの過程)を主眼におくか』で、切り口が変わってくるのではないかと思います。
それぞれについて、簡単なケースを想定してみることにしましょう。
最初は『プロセスを主眼』にやってみます。
まず現実的な話として、目標達成するためには、何らかのアクションが必要です。
自分がその『アクション』のために、プライベートでどれくらいの時間を割けるかを考えるところからスタートです。
例えば1日の中、もしくは週でも月でもいいのですが……あまりスパンが長いと厳しいので分かりやすく『1週間』にしておきましょう。
その中で、完全なプライベート・余暇として過ごせる時間が、どれくらいあるかを考えます。
今回は『4時間』とれると想定しましょう。週末に2時間ずつとれる、というイメージでとらえてみてください。
この4時間の内、目標達成のためのアクションに使ってもいいな、と思う時間を決めてみます。
フルに4時間勉強したって悪くはありませんが、趣味のあれこれをしたりする時間を全部取り払うのは、多趣味な私には非常に苦痛なので、ここは『1時間』としておきます。
この週・1時間――月間4~5時間という量で、達成できそうな目標を『年間の目標』とすれば、比較的達成がし易いのではないでしょうか。
勿論、ゴールを低くしろという訳ではありません。
あくまで『年間目標』の話ですので、今年はここまで、来年はその続きから…と、少しずつ、着実に歩を進めれば良いと割り切っておきます。
例えば、エンジニアのみなさんにはお馴染みかもしれない100本ノック系問題集を履修し、言語習得することを目標にしたとします。
100問を12ヵ月で完了するには、月平均で8~9問の履修が必要です。
ですが、最初のうちは設問も簡単で、サクサク8問程度終わる可能性がありますが、大抵こういうものは、進むほどに難易度があがり、1問解くのに何時間もかかる可能性だってありえます。
さてここでネックになるのが『週に割ける時間』です。
1問1時間かかると、週に1時間の勉強時間では、1ヶ月に4問しか終わらず、予定の8問には全く届きません。
ここで重大な選択を迫られるのが、月の勉強時間を増やすのか、それとも、月に解く目標数を減らすのかという事です。
ここで勉強の時間増を選択しても良いですが、勉強時間の量は変えず、生活リズムを守る方を選んでも、決して間違いではないのです。
問題が60問目あたりから急に難易度があがるようであれば、最初の5ヶ月は月に10問ずつ解く、6ヶ月目からは、週に1問、最大月4問勉強する。
そうすると、7ヶ月×4問=28問で、100問達成には12問届きません。
でも、それは来年の序盤3ヶ月で実行するという『来年の目標』に入れたっていいのです。
自分に無理のないペースで続けることができれば『勉強するの嫌になったなー』などの、目標を達成するアクションにマイナスイメージを抱くことも減るでしょうし、時間はかかっても、完了したときの達成感は、より大きく感じられるのではないでしょうか。
まずは『定期的に、自己研鑽の時間を取ることを習慣付ける』ことからスタートすることを、三日坊主派かもしれない方(私を含む)にはお勧めしたい所存です。
最初はなかなか守れないかもしれません。でも、このペースが無理なく守れるようになったら、目標達成はもう目の前に迫っているのではないかと思いますよ。
――こんな風に、自分に無理なく過程をクリアていうことのできる目標ならば、やってみてもいいかなぁと、思えませんか? どうでしょう?
さて今度は、ゴールを主眼として考えてみましょう。
○月○日に実施の資格試験合格を目標として勉強を行う、なんてものが分かり易いゴールだと思うので、これを例に考えてみてみましょう。
受験日が決まっているので、決められたら締切を守るのが得意な方には、楽勝な目標の決め方かもしれません。…た、たぶん?
今回の例の試験は『選択式のテストで、8割正解で合格』がボーダーなものとします。あくまでケーススタディなので、複雑にしても良いこと無いですからね!
というかそこまで決める意味はあまりなかったことに後で気づきましたが、気分を盛り上げるためにこのまま進めます。
そしてこの資格試験には、過去問題集(書籍)と、Webでの模擬試験(有料だが、一定期間内は何度でも繰り返し受けられる想定)があるとします。
目標を決めた日から試験日までは約10ヶ月の余裕があります。
模擬試験は最後の1ヶ月に繰り返し利用すると想定して、残りは9ヶ月。この間に、過去問題集を黙々と解いていく形で勉強をしていく予定を立てます。
問題集の総ページ数、または章の区切りをもとに、1ヶ月あたりどれくらい解いていけば、9ヵ月で1冊クリアできるのか…と決めるのもいいですが、ここは敢えて6ヵ月(つまり半年)で1冊制覇するように考えます。
浮いた3ヶ月は以下の2つに使います。
①解いていて、難しいと思った範囲の追加学習
②問題集全体の振り返り
①、②をどんな配分にするかは人それぞれですが、振り返りは模擬試験でもある程度まかなえるので、①多めがいいのではないかと思います。
これは昔、私がテストを受けて「あーーー、解けなかったところ、もーちょい深く学べばよかった!」と反省することが多かったので、ちょっとそれを思い出して設定してみました。自分は一発で全問正解したから問題ないわ、という猛者は、マイペースに進行してくださいませ。
まあそんな感じで大雑把な配分を終えたら、次は問題集を解くために必要な時間の捻出です。
ゴールというか、受験日は決まっているので、設定した量を進めるには、1日何時間勉強すればいいのか、を考えていきます。
解く問題集の量にもよりますが、先に例に挙げた『プロセス主眼』よりも、きっと時間の負担は大きくなるでしょう。ですが、ゴールに至るまでにはどうしても必要なことなので、時間をやりくりして学習時間を捻出していきます。
この場合、よりいっそう厳密で、しっかりとしたスケジュール管理が必要になってくると思います。
10ヶ月の間には、体調を崩す費だってあるでしょうし、急な予定が入って、うまく勉強時間を取れなかった月も出てくるかもしれません。
そういった不確定要素を見越して、時間がある日はちょっとだけ解く問題を増やしたり、早め早めの進行を心がけるのも、大事になってきそうです。
こういった『日々の調整』がどれくらい出来るかが、ゴールが決まっている際の目標達成のポイントでもあると思っています。
例えば問題集が300ページ数あったとして、6ヶ月で終わらせるには、単純な割り算で月50ページずつ進める必要があります。
1日2ページ解ければ余裕でクリアできる量ではありますが、じゃあ本当に毎日できるのでしょうか? 自身の生活リズムや、仕事の状況などを考えて、ある程度の余裕は持ちつつも、無理しないスケジュールを考えるべきでしょう。
この辺は、エンジニアのみなさんなら日々の作業進捗と変わらない管理方法になりそうですね。ご自身にあったやり方で、進捗を守っていくのが良いかと思われます。
そんな感じで頑張ってみても、不慮の事態というものは往々にして生まれるものです。
如何ともし難い理由で大幅に予定が狂った時の最終手段として『受験日を変える』というのもありますが、なるべくなら使わずに済ませたいものです。
というか、それを1回やると、ずるずると「次でいいかー!」と楽な方へ流れがちなので、本当にどうしても駄目だった、という時以外は、極力、元来のスケジュールに戻す努力をした方がいいです。
スケジュール管理の方法については、大分話がずれてしまうので、今回は略させて頂きますが、決めたペースを守り、学習を継続した結果して、無事に受験を迎えることが出来れば、目標は限りなく達成に近づいているはずです。
さて、こうやって『プロセス』『ゴール』2つの視点から目標達成を考えてみましたが、みなさんはどちらの方が、自分ではやりやすいと思われましたか?
私はどちらかというと、前者のプロセスから決める方がやり易いタイプです。
目標は、夢ではありません。
自分で努力して、叶え、掴み取るものです。
自分がこれから歩んでいく道標として、何らかの目標を決めなければいけないとなった時、多分慣れていない方は、相当迷うと思います。特に新入社員の方や、社会人になって間もない方は、目標と言われてもピンとこないのではないでしょうか。
正直なところ、私も往々にして悩むことが多いです。どれだけ年を重ねても、将来について考えるときは、色々考えすぎてしまうこともあったりして、すぱっと目標を決めることが出来ない場合もありますし、思ったように習熟を進められないこともあります。
ですが、何かをやろうと決めて、その1年後。なにも変わっていないのはただの停滞に他なりません。
最初は小さな事からで大丈夫です。
自らの成長を促すために、『自分が達成できる』、そして『達成してみようと思える』目標を考えてみてください。
ただ『会社から言われたから、目標を決める』のではなく、なるべくご自身が前向きに、目標と向き合って貰えたら嬉しいです。
去年の自分より、なにかひとつでも、ふたつでも、新しく出来ることが増えていると、それが自信に繋がりますからね!
弊社の目標設定は10月開始~翌年9月で終わりなので、ちょうど期間の半分が過ぎようとしているところです。
皆さんの半年の歩みは如何でしたか?
ちょっとだけ、このタイミングで振り返ってみませんか。
一度決めたはいいものの「なんかコレじゃないなぁ」とか「うまく進まないなぁ」など悩んだ時は、弊社エンジニアのみなさんは、まず所属ユニットの上長に相談してみてください。
年間目標に寄り添うのは、目標を決めた時と、期末に振り返りをするときだけではありません。
個人的には、相談は所属ユニットの枠を超えてもいいと思っています。
たとえば上長が自分の学びたい言語に詳しくないけど、他ユニットの人には詳しい人がいる、なんて時は、詳しい人に話を聞いてみるのも、新たな学びがあって良いと思います。
詳しい人に心当たりが無いときは、上長に尋ねてもらえれば、誰かいないか探すのでお気軽に相談してくださいね。
そして4月から新年度となる皆さまも、是非、春の始まりと共に、年度の目標を考えてみてはどうでしょうか。
来年の桜の咲く時期に、パワーアップした自分と出会えるかもしれません!